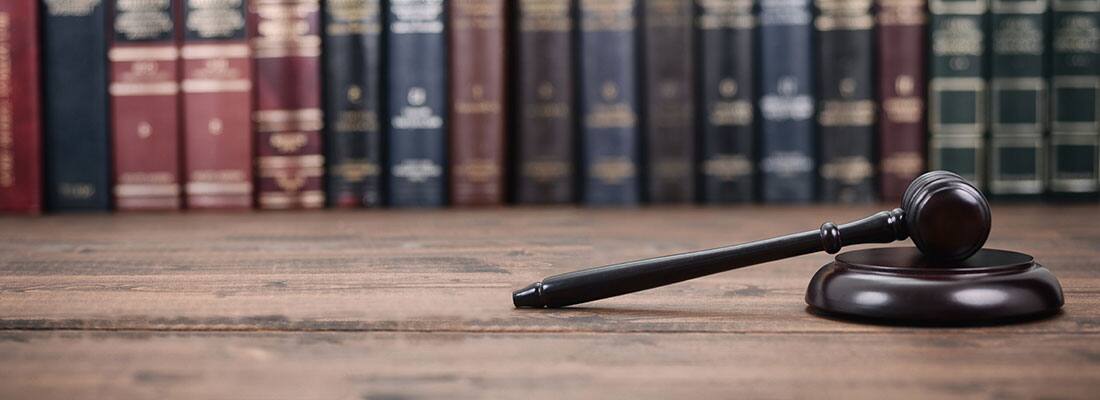PR
2012年の逗子ストーカー事件の要約記事です。
ストーカー規制法の初めての改正につながったこの事件のあらましを紹介しましょう。
法律がテクノロジーに追いついていなかった問題、探偵業法違反など、派生トピックの多い事件です。
逗子ストーカー殺人事件
事件の概要
神奈川県逗子市の自宅でフリーデザイナーの女性が以前に交際していた男に刺殺されたものです。
女性が男性との関係を断った直後からストーカー行為は始まりました。
その後、女性は別の男性と結婚して住所も変わっていたのですが、それを突き止めての犯行でした。
男は犯行直後に自殺したため、事件の過程の詳細は不明な部分も残されています。
この事件では、警察の秘密漏洩、探偵の人探しの悪用への協力もあって問題になりました。
2000年にできたストーカー規制法が、電子メールを使ったストーカー行為を取り締まれないことも問題になりました。
法律もテクノロジーの進化に対応しなければならないということです。
この事件を受けて、ストーカー規制法の第一回改正が行われました。
事件の経緯
 ストーカー行為のはじまり
ストーカー行為のはじまり
被害者女性Aと犯人男性Bは2004年頃から交際を始めましたが、2006年に女性から関係を断ちました。
それ以降、Bから嫌がらせのメールが来るようになりました。
 被害者の結婚と転居
被害者の結婚と転居
Aはその後、別の男性と結婚して逗子市に転居しましたが、Bには何も伝えていませんでした。
しかし、BはAのSNS投稿からAが結婚したことを知りました。
ここからBの嫌がらせがエスカレートし、刺殺するなどと脅迫するメールが毎日100通近く届くようになりました。
 犯人は一度逮捕・有罪に
犯人は一度逮捕・有罪に
Aは警察に相談し、Bは脅迫容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けます。
ストーカー規制法に基づくBへの警告も出され、Aの自宅には防犯カメラが設置されました。
 連続メールへの警察の不対応
連続メールへの警察の不対応
その後も膨大な嫌がらせメールが届くのですが、警察は犯罪に当たらないとして何の措置も取りませんでした。
メールの内容が脅迫などの明白な犯罪ではなく、結婚の約束?を破ったことに対する損害賠償請求だったからです。
連続電話や連続FAXはストーカー規制法で「つきまとい行為」として禁止されていましたが、連続メールは対象外でした。
 嵐の前の静けさ
嵐の前の静けさ
しかし、嫌がらせメールがある時パタリと止みました。
Bは諦めたわけではありませんでした。
逮捕前からYahoo知恵袋を活用し、あらゆる手段でAの住所の特定を試みていました。
探偵を使って住所を突き止めることに成功したこともわかっています。
おそらく住所がわかったから、嫌がらせメールをやめて次の行動準備に移ったのでしょう。
 殺人と犯人の自殺
殺人と犯人の自殺
Aはもう大丈夫だと思って借りていた防犯カメラを返却しましたが、その直後に事件は起きました。
殺害後にBは事件現場アパートの2階の出窓に紐をかけて首吊り自殺しました。
この事件で浮彫りになった問題点
 警察による個人情報漏洩
警察による個人情報漏洩
BがAの結婚を知ったのは、AのSNS投稿によってですが、結婚後の姓と住所は知りませんでした。
何で知ったかというと、警察の逮捕状執行です。
Bの前で逮捕状を読み上げる中で、Aの新しい姓名と転居先の市名を言う失態を犯してしまいました。
これに対して批判もありましたが、逮捕する時に「どこの誰に対する犯罪の容疑なのか?」を言わないのも問題があります。
あいまいな容疑で逮捕できるようになったら人権侵害につながるリスクが出てきます。
この事件以後、警察はこの問題への対応方法を試行錯誤しているようです。
 探偵の違法調査
探偵の違法調査
Bは興信所にAの住所を突き止める調査を依頼し、正確な調査結果を受取ったことがわかっています。
 探偵業法違反
探偵業法違反
ストーカー目的など、違法な目的の調査をすることは探偵業法違反です。
まず同法第7条は、依頼者から「違法な目的ではない」旨の誓約書を取ることを義務付けています。
また同法第9条は、調査が違法な目的であることを知った時は調査をしてはならないと定めています。
つまり、契約前に違法な目的でないことを依頼者に確約してもらうことが必要であり、調査開始後でも違法な目的であるとわかった時点で中止する義務があるのです。
状況からストーカー目的であることは容易に判断できたはずです。
この興信所のやったことは明かな探偵業法違反です。
 住所調査の手口
住所調査の手口
朝日新聞デジタルの記事によれば、この件で逮捕されたのは探偵業の男2人。
「TCC―OFFICE」代表の小浜博敏(59)=東京都品川区平塚2丁目=と、「アスク・ミー」社長の菊嶋毅(42)=東京都世田谷区玉川4丁目=の両容疑者です。
京葉ガスの相談窓口に名義人である被害者の夫を装って電話。
「料金を払っているのに請求書が届いた」などと言いがかりをつけ、やりとりの中で名義人の氏名を聞き出したそうです。
依頼から2時間で目的の氏名の入手に成功したそうです。
 探偵業界への影響
探偵業界への影響
ちなみにこの事実の発覚により、探偵に対する世間の風当たりが非常にきつくなりました。
探偵に人探しを依頼すること自体が悪とみなされる状況がしばらく続いたのです。
これ以降、家族の依頼による家出人探し以外の人探しは受任しない探偵社が増えました。
 探偵業界の新たな試み
探偵業界の新たな試み
この事件を受けて、JCIという探偵社の代表・宮岡大さんが「SAVE ME」というホームページを立ち上げました。
ストーカーが所在調査を依頼してくる際は、以前の住所を提示することが多い。
そこでストーカーの被害に遭っている人に以前の住所を登録してもらい、加盟探偵社で共有していこうというものです。
報道時点では加盟は40社で、業界団体や警察との連携も考えていきたいとのことでした。
 地方自治体の個人情報管理の杜撰さ
地方自治体の個人情報管理の杜撰さ
上述の興信所がAの正確な住所を調べた方法は、逗子市役所に偽りの問い合わせをする手法でした。
市役所の納税課職員はやすやすと騙されて、Aの情報を提供してしまいました。
後の調べで、この職員だけが問題なのではなく、部署の個人情報管理自体が非常に杜撰であることが判明しました。
 法律の時代対応の遅れ
法律の時代対応の遅れ
ストーカー規制法が、当時すでに普及していた電子メールを使ったストーカー行為に対応していない問題も浮き彫りになりました。
テクノロジーの進歩とともに生活も変化していき、犯罪の手段も変わっていきます。
特にインターネット時代に入ってその変化は加速しています。
時代に合わせて法律もアップデートしていかないと使い物にならないことがハッキリした事件でもありました。
ストーカー規制法 第一回改正
2000年にできたストーカー規制法が上述の問題の反省を受けて、初めて改正されました。
連続電話や連続FAXだけでなく、連続メールも「つきまとい行為」に加えられました。
しかし、ストーカー規制法の時代への対応はこれで十分ではなかったと後日判明します。
2016年に起きた小金井ストーカー殺人未遂事件では、同法がSNS上のストーカー行為に対応できていない問題が浮かび上がります。
この事件は2回目の法改正に結びつきました。
追記
 被害者のお兄さんの話
被害者のお兄さんの話
加害者が自殺しているために憎しみをぶつける対象がなく、ただ悲しみが残ったそうです。
しかし、悲しんでいるだけではダメで、再発防止に向けて何かしないといけない。
そう思って被害者の声を司法や行政に届けるため、『ストーカー対策研究会議』を立ち上げました。
 被害者のだんなさんの話
被害者のだんなさんの話
2人は事件が起こる4年前、2008年に結婚し、雑貨作りのワークショップなどを企画する会社を経営していたそうです。
警戒不十分への後悔
元カレがしつこいメールを送ってくるのは知っていましたが、まさか殺しに来るとは思わなかったとのこと。
奥さんも気にするそぶりなど見せなかったそうですが、周囲を心配させまいとの気遣いもあったのかもしれません。
そこに気づいてあげられなかったのが悔しいということです。
犯人は犯行直後に自殺しているため、その気持ちは聞けません。
市を提訴・責任認める判決
市民の秘密を漏洩させた責任を明確化するために、1100万円の慰謝料を求めて逗子市を訴えました。
裁判を傍聴し、違法な調査をした探偵と、秘密を洩らした市役所の納税課の男の答弁を聞きました。
探偵は調査の実行を否定し、役人は「記憶にない」を繰り返すのを、ただ残念に思ったそうです。
横浜地裁横須賀支部は、逗子市に110万円の支払いを命じる判決を下しました。
金額は請求額を大きく下回りましたが、だんなさんは控訴しませんでした。
市の責任が認められ、ミスをしたら責任が問われることがはっきりしたことに、満足したそうです。
事件から10年後
だんなさんは事件から10年になる2022年にメディアの取材をうけています。
今も夫婦の思い出が詰まった街で暮らしておられます。
事件後に見つけた奥さんのノートには、「子供2人、家を建てる」という10年後の夢が書かれていました。
市を相手取った民事裁判に勝訴し、ストーカー規制法も改正されました。
しかし、事件の風化は懸念しており、捜査機関や行政機関には決して忘れてほしくないとのことです。
 自業自得説
自業自得説
このように被害者には何の非もない悲惨な事件なのに、「自業自得」とするような書き込みがあるようです。
言葉の意味を理解して書いているのでしょうか?
書き手はストーカーに共感を感じる、似たところがあるような人なのでしょうか?
非常に残念だし、悲しいし、憤りを禁じえません。
ストーカー対策は探偵の活用も視野に
 ストーカー規制法で大きく改善したが・・・
ストーカー規制法で大きく改善したが・・・
ストーカー規制法以前には、傷害や殺人などの事件が起きるまで、警察は何もしてくれませんでした。
それに比べると今日ではかなり守ってくれるようになっています。
ストーカー問題に対しては、法律も警察も徐々に進歩しています。
ただ、その歩みはとても緩やかなのです。
 繰り返される事件と法改正
繰り返される事件と法改正
ストーカー規制法ができて12年も経つのに、この逗子ストーカー殺人事件のような事件が起きているわけです。
そして、これで終わりではなく、この4年後にまた小金井ストーカー事件が起きるわけです。
そこから長い年月を経た現在、警察も進歩はしているでしょうが、また不備な対応をしてしまうリスクは残っています。
 探偵を使った自衛策の検討
探偵を使った自衛策の検討
もしあなたがストーカーの被害に遭い、警察に相談に行ったが満足な対応をしてもらえなかった場合にどうするか?
その時は探偵の活用も考えてみてください。
ストーカー行為の動画など証拠を取り、相手の住所も突き止めた上で警察に相談するのです。
警察は間違いなくより真剣にスピーディーに対応してくれるはずです。
※本ページには広告リンク(PR)が含まれていますが、内容は取材や独自調査にもとづき、中立性を保持しています。
最終更新日:2026/1/15
更新責任者:徳野 制
管理記号:1