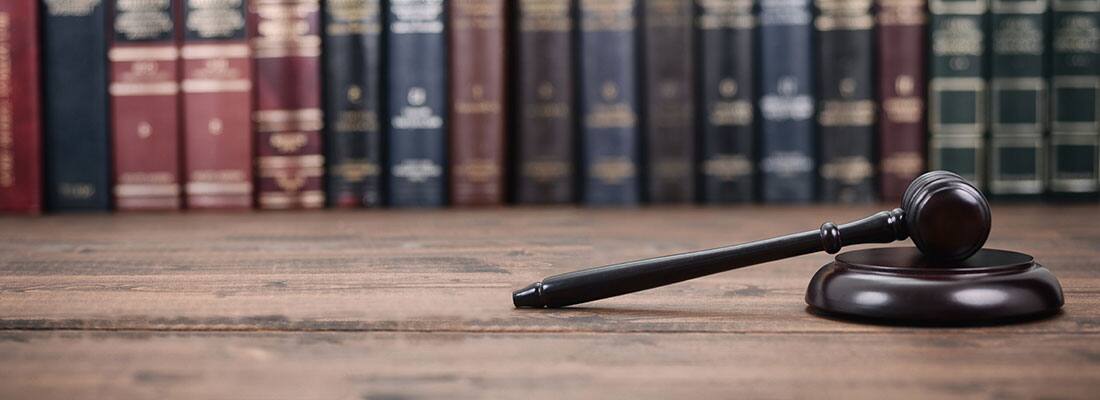PR
2016年、東京小金井市で起きたストーカーによる殺人未遂事件についてまとめています。
ストーカー防止法施行から16年を経てなお警察の対応に不備があることを示した事件です。
小金井ストーカー殺人未遂事件
事件の概要
2016年、東京小金井市で芸能活動を行っていた20歳の女性が刺され、重体に陥った事件です。
一命はとりとめたが、深刻な後遺症が残りました。
犯人は犯行に先立ってTwitterなどのSNSでストーカー行為を繰り返していました。
しかし、警察の対応は危機感に欠け、またSNS上での問題行為に適切に対応できませんでした。
2000年にストーカー規制法ができてから警察の対応は昔よりは改善はしていました。
しかし、法の施行から16年を経てなお意識の改革が不十分だったということです。
そしてインターネットテクノロジーの進化に合わせて法律も進化し続けなければならない。
そのことを改めて明らかにした事件とも言えます。
事件発生と同じ2016年、2回目の法改正が行われました。
事件発生までの経緯
 被害者女性A
被害者女性A
被害者の女性Aは東京都内の私立大学に通う女性。
女優やシンガーソングライターなどの芸能活動を行っていました。
あくまで学生の芸能的活動でプロではありません。
 被害者Aはアイドル?
被害者Aはアイドル?
確かにアイドル的活動をしていた時期もあります。
それで事件当初は「アイドル刺傷」とか「地下アイドル刺傷」と報じられましたが不正確です。
第三者の抗議でメディアは事実誤認を認め、後の報道ではアイドルという見出しはなくなりました。
 ストーカー男B
ストーカー男B
犯人の男Bは群馬県出身、京都市在住の会社員。
Aのファンになって最初はTwitterで好意的なつぶやきをしていました。
しかしだんだん直接つながろうとし始め、一方的にプレゼントを送りつけます。
それを無視されたことに怒り、今度は返却を要求しました。
Aが要求通りに返送したことでBはさらに逆上し、殺害計画の動機になりました。
 杜撰な警察の対応
杜撰な警察の対応
不穏な内容に変化していったTwitterに関してAは武蔵野署に相談しました。
しかし、同署は一般相談として処理し、ストーカー事案を一元管理する専門部署に連絡しなかった。
Aの母親は京都府警にBの行為を止めてほしいと相談しましたが、警視庁に相談するように言われただけでした。
Bは以前にも別の複数の女性に対するSNS上のストーカー行為で警察に相談が入っていた人物でしたが、情報共有していませんでした。
このように警察の対応は危機感が希薄で、組織内の連携を欠いたものでした。
 事件当日の出来事
事件当日の出来事
そして事件当日、Bは小金井市のライブハウス付近でAを待ち伏せて接触しました。
長時間、張り込んでAの到着を待っていたのです。
そして声をかけ、口論になります。
Aはその場で110番しますが、警察は現在位置を確認せずに自宅に警察官を派遣します。
Aは万一に備えて110番緊急通報システムに登録しており、そこに自宅情報が記載されていました。
だからシステムに表示された場所が事件現場だと思い込み、現在位置確認を怠ったのです。
事件はライブハウス前で起きようとしているのに、自宅に向かったのです。
正しい現場に警察官が向かったのは事件の目撃者の通報を受けてからでした。
口論の末、用意していたナイフでAを20ヵ所以上刺していたBは傷害容疑で現行犯逮捕。
Aは緊急搬送されましたが、一時心肺停止状態になり、その後も意識不明の重体が続きました。
事件発生後の経緯
Bは容疑を殺人未遂と銃刀法違反に切り替えて送検され、起訴されました。
Aは最終的に意識を回復しますが、退院後も重い障害が残りました。
東京地裁立川支部での裁判で、Bは起訴内容を大筋で認めますが、計画性については争います。
法廷での態度は、第三者の目には反省が感じられないものだったといいます。
求刑17年に対して懲役14年6カ月の判決が言い渡され、Bはいったん控訴するも取り下げて刑が確定します。
追記
事件発生から時間が経って、いろいろな情報が公開されています。
 加害者
加害者
加害者は京都市右京区の造園業、岩埼(いわざき)友宏。
身長180cmの長身で、十代の頃は柔道に打ち込んでいたようです。
中学の時には県大会で優勝し、高校にはスポーツ推薦で入学したのだとか。
かなりの腕力だと思われます。
武器を持っていなくても、こんな男に襲われたら、女性は抵抗できないですね。
家族の証言では、「真面目だが、感情表現が苦手。ため込みやすく、感情を爆発させることが多かった。」とのこと。
また、過去にAV女優波多野結衣のバスツアーに完全素人として参加していたことがわかっています。
性欲が非常に強いが、女性とうまく接することができず、自己中心的で暴力的な対応しかできなかったのでしょう。
謝罪はあったそうですが、懲役14年6カ月が確定。(東京地方裁判所立川支部)
彼は現在服役中で、2023年ごろには出所すると思われます。
 被害者
被害者
被害者は、亜細亜大3年生の、冨田真由さん(20)(当時)。
学業のかたわら、女優やシンガーソングライターとして活動していました。
事件当時は「アイドル刺傷事件」と報道されましたが、専業アイドルではなく、誤認です。
一時は心肺停止状態に陥ったようですが、懸命な治療により、一命をとりとめたようです。
しかし、片目の視野が狭くなる後遺症が残り、好きな読書をしても、全然頭に入ってこないそうです。
また、精神面の後遺症、PTSDもひどく、男性恐怖症などがあるようです。
無理もありません。
警察や法律への影響
 いまだ危機感を欠く警察
いまだ危機感を欠く警察
世間では過去のストーカー事件の教訓が生かされていないという警察批判が高まりました。
そもそもストーカー規制法は、警察の怠慢で防げるものを防げなかった桶川ストーカー殺人事件をきっかけに作られたものです。
この事件は、明白な危険が迫っているにも関らず、警察官が相談者を真剣に保護しようとしなかったために起きました。
そして事件発生後も保身に走り、事実を改竄していたことが暴露されました。
結果、この事件では3人の懲戒解雇を含む15人の処分がなされました。
小金井ストーカー事件における警察の対応はそこまではひどくありません。
しかし、ストーカー規制法施行から16年を経ても先述したような危機感のなさ、連携の不足です。
世間の批判も無理のないことです。
 法律の現代社会への対応の遅れ
法律の現代社会への対応の遅れ
この事件では警察の体質の問題のほかに、法律の穴があぶりだされました。
2012年の逗子ストーカー殺人事件での反省を受けて行われた1回目のストーカー規制法改正。
そこでへ電子メールを用いたストーカー行為が規制対象に含まれました。
しかし、法律のインターネットテクノロジーへの対応はそれだけでは不十分だった。
小金井ストーカー事件ではSNSへの対応が急務であることが浮かび上がりました。
2016年の2回目のストーカー規制法改正で、SNSを用いた付きまとい行為が規制対象に加えられました。
探偵の利用も検討すべし
このようにストーカー規制法から10年以上の歳月を経ても、警察の対応は適切な水準に進歩していませんでした。
逗子ストーカー事件と2013年の第一回法改正、小金井ストーカー事件と第二回法改正、そしてその後の数々のストーカー事件。
そうした経験を経て、もちろん警察の対応も改善はしていっているはずです。
しかし、都道府県や署によって温度差はあるはず。
そして警察にその気があっても法のほうが社会の進歩に追い付いていないために適切に動けないことは今後もありえます。
たとえばメタバースを使ったストーカー行為に今のストーカー規制法は対応しきれるのでしょうか?
このような背景もある中で、あなたや周囲の人がストーカー問題を警察に相談に行った場合、どうなるか?
非常に不満足な対応で、不安が解消されない事態は今も起きうるのかもしれません。
その時は探偵の活用も考えてみてください。
探偵を使ってストーカー行為の証拠と相手の住所を押さえてしまうのです。
それらを添えての訴えには、警察の対応の真剣味やスピードも変わってくるはずです。
おすすめ探偵社

【クロル探偵社 相談室】
ストーカー規制法施行から20余年。
警察の対応はかなり改善されましたが、鈍い対応をされて、手遅れになることはまだあるようです。
証拠を押さえた上で被害届を出すと、対応が早まります。
おすすめの探偵社を紹介します。
総合探偵社クロル
総合探偵社クロル 探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30210097号
高品質調査をリーズナブルに提供し、契約を急かさない気軽な相談をモットーとする探偵社。
浮気調査に限らず、幅広いトラブル相談に乗れる「人生のかかりつけ医」を目指している。
池袋本社で全国6拠点。
東京都池袋(本社)/北海道札幌市/埼玉県霞が関/大阪市北区/名古屋市中区/岡山市北区
MJリサーチ
MJリサーチ 探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30200349号
大手探偵社で長い経験を持つ探偵たちが創設した探偵社。
大手並みのしっかりした調査を大手より3~4割安く、リーズナブルに提供するポリシー。
多様な困りごとに対応し、ユーザーとは1回限りでなく、繰り返し使ってもらえるお付き合いをしたいと考えている。
本社は銀座の隣町で、全国11ヶ所に展開。
本社(新富町 銀座の隣町)/銀座支店/品川支店/練馬支店/埼玉支店(大宮区)/新潟支店/群馬支社(太田市)/群馬高崎支店/福島支店(郡山市)/名古屋支店/大阪支店
※本ページには広告リンク(PR)が含まれていますが、内容は取材や独自調査にもとづき、中立性を保持しています。
最終更新日:2026/1/15
更新責任者:徳野 制
管理記号:1