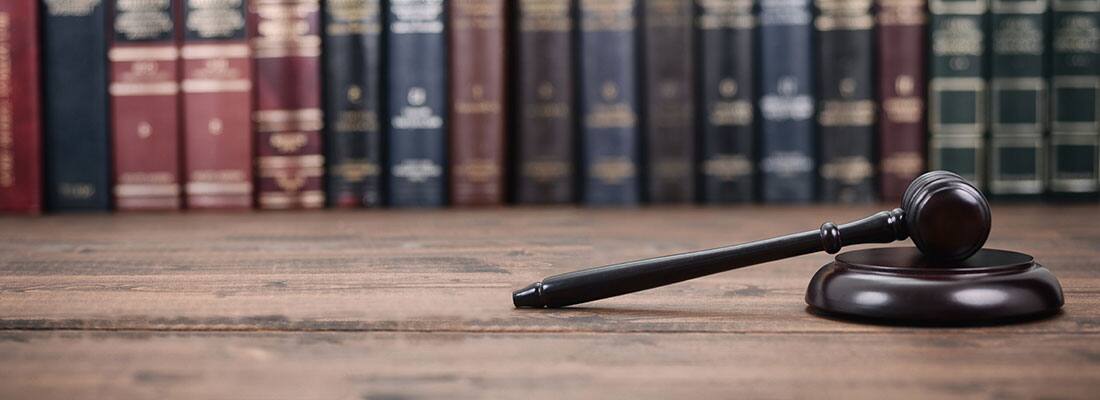
PR
ストーカー規制法はいつどんな契機で作られたのか?
今日に至るまでの改正の歴史は?
そういう基礎知識を解説します。
ストーカー規制法の立法と改正
【キャバ嬢のストーカー対策|当社動画】
ストーカー規制法以前
2000年に同法ができる以前は、警察はストーカー案件に関しては傷害・殺人などの犯罪が実際に起きるまで何もしてくれませんでした。
ストーカー案件は「痴情のもつれ」という奇妙な警察内用語で片付けられていました。
「あ、それは『痴情のもつれ』だから警察は介入しない。当事者の話し合いで解決してもらって。」という具合です。
「痴情のもつれ」は現実にかなり危険な状況になっていても「民事」と決めつけられていました。
そして、警察は「民事不介入」を理由に対応しなかったのです。
その状況下で何度も暴力沙汰が起き、世間でも警察の対応方法に対する問題意識が高まっていました。
桶川ストーカー殺人事件
そして1999年暮れ、ついにこの事件が起きます。
埼玉県桶川市の駅前で女子大生がストーカーの手下に刺殺されたものです。
ストーカーは女子大生の関係断絶を恨み、事件に先立って近所や学校などですさまじい嫌がらせ行為を行いました。
そして殺害は計画的かつ組織的でした。
被害者と家族は何度も警察に相談に行きましたが、無気力でずさんな対応をされました。
ストーカー行為は極めて悪質で、危険な兆候に満ちていたのに何もしなかったのです。
さらに事件後も母親をすぐに病院に行かせなかったり、応対記録を改竄しようとしたり、犯人の指名手配が遅れたりといった有様でした。
この腐敗ぶりがジャーナリズムに暴かれ、3人の懲戒免職を含む15人の処分者を出す一大警察不祥事になりました。
報道を受けてこの事件が国会でも取り上げられ、ストーカー規制法立法の機運が一気に高まりました。
ストーカー規制法成立
事件の翌年、議員立法により2000年にストーカー規制法が成立します。
「つきまとい等」という名称でつきまとい、監視、無言電話等の嫌がらせ行為を違法と定めるものです。
そうした行為を特定の相手に繰り返す「ストーカー行為」に対する罰則も設けられました。
警察にストーカーを止めに入るお墨付きが出たわけです。
しかし、この法で警察の対応が一気に変わったわけではありません。
ストーカー被害に一応対応はするものの、しばしば危機感と組織内の連携に欠けていました。
そしてストーカー規制法も世の中の変化に追いついていない部分があると後に判明します。
さらなる犠牲が出ないとこうした問題を改善できませんでした。
ストーカー規制法第1回改正
法の第一回改正は、逗子ストーカー殺人事件が契機となりました。
2012年、神奈川県逗子市の自宅で、女性が当時の夫と結婚する以前に交際していた男に刺殺されたものです。
男は女性の結婚に怒り、あらゆる手段で転居先を突き止めて犯行に及びました。
この事件では警察や市役所が不用意に転居先の情報を漏洩してしまう事態が見られました。
そして犯人が転居先の情報入手に探偵を使ったことも大きな問題になりました。
ストーカー被害の防止にはストーカー規制法だけでは十分ではない。
警察や自治体その他の個人情報管理や探偵の規制なども重要だと判明した事件です。
また、この事件では犯人が大量の嫌がらせ電子メールを送っていたのに、警察が制止しなかったことが問題になりました。
当時のストーカー規制法が電子メールに触れていなかったため、警察は違法性はないと判断したのです。
すでに電子メールはごく一般的な連絡手段になっていたにも拘らずです。
テクノロジーの進化とともに人々の生活は変わるので、法律もそれに合わせたアップデートが必要である。
そんな教訓が得られた事件でした。
翌2013年の1回目の法改正で、電子メールによる付きまとい行為が加筆されます。
ストーカー規制法第二回改正
2回目の法改正は、小金井ストーカー殺人未遂事件が契機となりました。
2016年、東京小金井市で女性がめった刺しにされ、一命は取り留めたものの深刻な後遺症を負った事件です。
この事件で当時のストーカー規制法がSNS上のストーカー行為に対応できていない問題が浮上しました。
テクノロジーの進歩への法対応は第一回改正だけでは不十分だったのです。
これを受けて事件と同年の2016年、2回目の改正が行われました。
SNSに関する項目が加筆されたほか、禁止命令関係は警察ではなく、公安委員会が出すように変更されました。
3回目 2021年改正
これは2020年の最高裁判決が、元交際相手の車に無断でGPSをつけて位置情報を知ることがストーカー規制法違反ではないとしたことを受けた改正です。
こんな判決が出てしまうのは法の不備だということで、GPSをはじめ、いくつかの問題に対する新規制が盛り込まれました。
ストーカー規制法の概要
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)は、ストーカーの被害を防ぐための法律です。
この法律ではまず「つきまとい等」に行為リストを定義。
それを特定の相手に繰り返し行うことを「ストーカー行為」と定義して規制しています。
法律と各回の改正の概要を紹介します。
つきまとい等(2016年改正版)
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく
- 監視している旨の告知等
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動
- 無言電話、拒絶後の連続した架電、またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
- 汚物・動物の死体ほかの送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を害する事項の告知等、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
こうした行為に対し、公安委員会は被害者の申し出に基づき、または独自の判断で禁止命令を出せます。
保護される対象は女性だけでなく男性も含み、また同性愛のストーカー行為も対象です。
罰則
| 対象行為 | 2016年改正前 | 2016年改正後 |
|---|---|---|
| 禁止命令より以前に「ストーカー行為」をした場合 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、かつ親告罪 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
| 禁止命令のその他の事項に違反した場合 | 50万円以下の罰金 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
つきまとい等行為の目的の限定
同法の第二条は、つきまとい等の目的を恋愛感情・好意またはそれが満たされなかったことによる怨恨に限定しています。
また相手も特定の者とその配偶者や家族などに限定しています。
こういう限定がないと法が拡大解釈されて、ストーカー被害を防ぐという本来の目的からはずれた運用をされる危険があるからです。
専門的な表現をすると、公権力介入の限定ということです。
3回の改正の要点
| 2013年改正(第1回) |
|
|---|---|
| 2016年改正(第2回) |
|
| 2021年改正(第3回) |
|
ストーカー調査おすすめ探偵社
ストーカー規制法ができて四半世紀。
ようやく各地の警察にもよく浸透して、被害者は守ってもらえるようになりました。
しかし、今もなお、対応が鈍かったり、不適切だったりすることはあります。
そういう時は探偵を使って証拠を押さえた上で警察に届けると、対応が早いです。
探偵のストーカー調査の内容と、おすすめの探偵社を紹介しておきます。
探偵のストーカー調査内容
主には次の3つです。
 所在調査
所在調査
つきまといが気になる場合は、住所を突き止めて警察に届ければ、対応が格段に速いです。
ストーカーが出没しそうな日時・場所に依頼者に出向いてもらい、探偵チームが張り込みます。
ストーカーが現れたら、帰宅まで尾行して住所を突き止めます。
 定点監視調査
定点監視調査
自宅へのいたずらや嫌がらせに悩んでいる場合に有効な手です。
玄関先などに隠しカメラを仕込み、証拠映像を撮ります。
 盗聴器発見
盗聴器発見
いろいろな外出先に出没するようなら、情報が漏れている可能性があります。
依頼者の自室を盗聴器発見器で調査し、見つかった場合は除去します。
おすすめの探偵社
下記の2社がおすすめで、下記のような共通点を持ちます。
- 大手有名社出身のベテランが中核で、腕は確か。
- 顧客の要望に柔軟に応じ、リーズナブルな価格設定
- ストーカー調査を含む幅広い経験を持つ
世の中の探偵は、浮気調査しか経験のない人が大半なので、③は大事です。。
 総合探偵社クロル
総合探偵社クロル
総合探偵社クロル 探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30210097号

【クロル探偵社 大原代表】
★全国6拠点(2023.8)
東京都池袋(本社)/北海道札幌市/埼玉県霞が関/大阪市北区/名古屋市中区/岡山市北区
フリーダイアル: 0078-6014-1009
 MJリサーチ
MJリサーチMJリサーチ 探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30200349号

【MJリサーチ若梅探偵】
★拠点一覧 2023.11現在 11ヵ所
| 本社 | 東京都中央区新富町(銀座の隣町) |
|---|---|
| 東京&周辺県 | 銀座支店/品川支店/練馬支店/西東京(立川)/埼玉支店 |
| 北関東・東北・信越 | 群馬支社(太田市)/群馬高崎支店/福島支店 |
| 中部・関西 | 名古屋支店/大阪支店 |
フリーダイアル: 0078-6009-0036
(※スマホからは上記番号をタップしてかけられます)
もっと幅広い選択肢を希望される方は、下記のページをどうぞ。
上記2社を含む大手有名探偵社を取材したレポートです。
※本ページには広告リンク(PR)が含まれていますが、内容は取材や独自調査にもとづき、中立性を保持しています。
最終更新日:2026/1/15
更新責任者:徳野 制
管理記号:1



