ピンカートン探偵社の謎
PR
探偵自身が書いた本や探偵のノンフィクションを紹介していくコーナーです。
本を通じて、この謎めいた探偵業界の実態を探ります。
今回、ご紹介するのは下記の本。
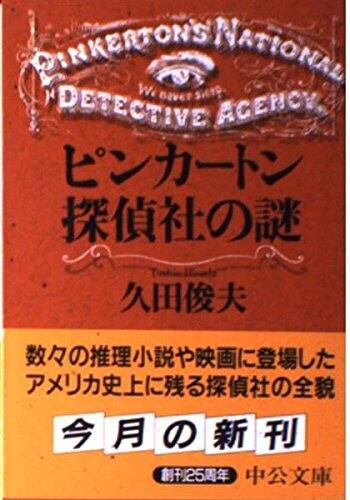
「ピンカートン探偵社の謎」 久田俊夫 著 中公文庫 廃刊
ピンカートン探偵社は、全米初の探偵社です。
アメリカの歴史に強い大学教授が、いろいろな資料を調べて書いた本です。
世界的に有名な探偵社ですが、日本では情報が乏しいので、貴重な本と言えます。
はしがき
ピンカートン探偵社は、1855年にイギリス系移民のアラン・ピンカートンによってシカゴで設立された全米初の探偵社。
コナン・ドイルの「恐怖の谷」の主役バーディ・エドワードはその工作員だし、「マルタの鷹」で有名なハードボイルド小説の創始者ダシール・ハメットは数年在籍したこともあり、昔の文学にはよく登場する名前です。
設立当初は、探偵というより資本家の私設警察ないし軍隊のような役割を担い、労働組合活動の破壊工作など汚い仕事をたくさん行っていました。
当時の探偵小説が、探偵を非合法な手段を厭わないながらも超人的正義漢として描いたことはその実態を覆い隠すことになり、同社はそれを利用しました。
社のロゴに記された有名なモットー「我々は眠らない(We Never Sleep)」もあいまって、謎めいた同社の仕事に魅力を感じる人は多かったようです。
こういう業種が成立したのは、公的警察の整備が遅れていた米国の特殊事情があります。
国家の介入と税負担を嫌う伝統のため、州をまたいだ警察の整備は社会の発展に追い付かず、人々は私的警察を頼るほかなかったのです。
その一方、犯罪資料の全国規模のデータベース化をはかったことは、現在の連邦捜査局FBIの基礎を作ったとも言われています。
ピンカートン社は、現在では警備保障を主たる業務として年商10億ドル強を計上し、世界20か国に220の支店を持ち、4万7000人の社員を擁する多国籍マンモス企業になっています。
本書は創業者のイギリス時代から、アメリカで労働スパイが非合法化される1930年代半ばまで――創業者から4代目まで――を扱っています。

【ピンカートン探偵社のロゴ】
プロローグ
ピンカートン探偵社はさまざまな有名事件との関わりの記録を残しています。
例えば、1875年頃のモリー・マガイアズ事件は、コナン・ドイルの小説「恐怖の谷」のモデルになり、ショーン・コネリーとリチャード・ハリス共演で「男の闘い」(1969年)として映画化されました。
ワイルド・バンチ強盗団の追跡は、ロバート・レッドフォードの「明日に向かって撃て!」という映画になりました。
有名事件はほかにもたくさんあります。
この会社の業務への需要と活躍の余地がそれだけ大きかったわけですが、当時の状況はどのようなものだったのでしょうか?
19世紀末のアメリカでは産業革命に起因する急速な経済発展と商業規模の拡大により、人々の活動は州境を超えて全国規模になりつつありました。
そこへ1849年に始まったゴールドラッシュやヨーロッパにおける飢饉を原因とした移民の大波が重なりました。
これほど経済発展や人の動きが全国規模になっていたのに、全国的な警察機能の発展はまったく追い付いていなかった。
そこには二大政党の勢力が拮抗して政権が不安定だったことや、裕福な市民が増税を嫌った特殊事情があります。
全国レベルの警察が順調に発達したカナダ、ニュージーランド、オーストラリアなどと大きく違う点です。
こうした中で資本家は私設警察を雇い、労働運動を阻害するなど、法を無視した好き勝手をするようになりました。
ピンカートン探偵社が雇っていたのは、金持ちの用心棒を喜んで引き受けるごろつきばかりでした。
当時は別の場で発展していた推理小説が作り出したイメージで実態が隠されていたのですが、時を経るにつれて卑劣な実態が暴露され、社会の強い批判を受けるようになりました。
その結果、ピンカートン探偵社は方向性を修正せざるを得なくなりました。
第1章 ピンカートン探偵社の起源
アラン・ピンカートンはスコットランドの貧困層に生まれ、幼くして父を亡くし、兄弟を養うために樽職人などとして働きました。
急進的な民主化政治活動「チャーチスト運動」に参加した後、警察の追及を逃れるために結婚したばかりの妻とともに渡米。
樽職人として暮らしていたが、偶然に贋金作りの野営地を発見して警察に突き出したことで、通貨偽造犯摘発の副業の道が開かれました。
その評判は高まり、やがて誘拐犯の逮捕や郵便局員の送金横領摘発の依頼も舞い込むように。
ピンカートンはおとり捜査などの手法で成果を上げます。
この頃、鉄道網が急速に発達しましたが、鉄道員の横領や友人の無賃乗車を許すなどの規律違反が横行していました。
しかし、当時の警察は局地主義で、州境を越えられてしまうと管轄外で無力でした。
全国的な公的警察は未発達だったので、摘発は私立探偵に頼るほかありませんでした。
1855年、アラン・ピンカートンは中西部の6つの鉄道会社の出資を受けて、ピンカートン探偵社の前身であるノースウェスト警察機構をシカゴに設立します。
この中で横領などの摘発だけでなく、労働スパイも大きな仕事になっていきます。
貧困層に生まれ、チャーチストでもあったピンカートンは労働者の敵になっていくのです。
1860年代に入ると、各地で中央集権的な警察の確立が進み、解任された以前の平巡査が私立探偵となって、公警察と激しく競合するようになります。
しかし、ピンカートン探偵社は公警察との協調姿勢を打ち出しました。
この頃、私立探偵制度に反対するウェントワース市長と警察署長崩れが創設したブラドレー探偵社が対立していましたが、ピンカートンはそういう政治抗争からも距離を取りました。
巡回警備を主業務にしていたブラドレー探偵社などと違い、ピンカートン探偵社はスパイ業務を主に成長していきます。
秘密主義に徹し、世間に活動の実態を知られることなく、逆にロマンチックな憧れの視線まで受けながら、活動の幅を広げていきます。
1860年代までにピンカートン探偵社は、アメリカ中西部の警察力を指揮して評判を高めました。
その結果、州の境界を越えて犯人を追跡・逮捕する全国規模の私立探偵社になっていきました。
それは本来は連邦警察が担当すべき分野でしたが、当時はそこが警察権のスキマになっていたのです。
第2章 南北戦争でジャンプ
アメリカでは鉄道の発達に伴って宅配便も発達しました。アメリカン・エキスプレスなどがこの頃に創業されました。
しかし、州境を越えて盗難や着服の被害に遭うと警察は無力だったので、何とかする必要がありました。
ピンカートン社は犯人の証拠集めを請け負い、裁判で有罪を勝ち取ってほぼ全額回収に成功したことで名を挙げ、この分野に進出します。
やがて南北戦争が始まり、鉄道と宅配便の発達を阻害しますが、ピンカートン社は今度は北軍のための内偵調査に商機を見出します。
その代表が「ボルチモア事件」で、巧みな工作でリンカーン大統領の暗殺を防ぎました。
高まる軍需に乗じた悪徳業者の詐欺事件摘発も行いました。
さらにはリンカーン大統領のもとで南軍のスパイを摘発する仕事も行いました。
その中で大きかったのは南部のバラことグリーンハウ夫人の一件で、摘発はしたもののその後の処理が大統領判断で甘かったため、ピンカートンは復讐され、部下を失います。
ピンカートンは、一時は北軍のシークレット・サービス部長を高額報酬で務めました。
ピンカートンは、二人の息子が戦争の熱狂に巻き込まれて兵士になったりしないように、工作員にしました。
二人の息子は偵察気球に乗ったり、南軍に入り込んだり、危険な任務を遂行しました。
1865年にリンカーン大統領は暗殺され、ピンカートンは「自分が現場にいればこんなことは起きなかった」と嘆きます。
戦後、ピンカートンはニューヨークとフィラデルフィアに事務所を開設し、戦時中に作った政府内へのコネを活かして事業を伸ばしました。
労務管理の重要度が増した世の中で、鉄道車掌の着服摘発をはじめ、労働スパイの事業が拡大していきました。
需要の増加に伴い、競合の私立探偵社も増えました。
ピンカートンの料金は法外でしたが、調査は周到でした。
しかし、競合にはやらずぼったくりも多く、社会の批判を浴びました。
探偵業界の市場競争が激化すると世間の人気が必要になり、ピンカートンは自分の仕事を美化する本を書くようになります。
10年間で16冊の本を書きました。
この時代に調査はもはや個人プレーではなくなり、チームを組んで軍隊のように計画的に行うようになり、通信も暗号化されます。
第3章 社内管理は女スパイに
ピンカートンは部下を工作員(operative)と呼び、自分のことは局長(principal)と呼ばせていました。
その仕事は探偵小説のような超人による個人プレーではなく、組織的なチームプレイでした。
南北戦争後の10年間、ピンカートンは会社の基盤固めと労務管理に力を入れました。
社内の管理には、ケイト・ウォーンのようなお気に入りの女探偵を活用しました。
この本は、1855年創立のピンカートン探偵社を「世界初の私立探偵社」とする説を否定しています。
1832年フランスのユージン・ピドクによる「調査局」の方が先だし、アメリカでもピンカートン探偵社創業以前にセントルイスに二人の警官が設立した私立探偵社があったそうです。
しかし、ピンカートン探偵社は組織を固め、企業として成長し、歴史に名を刻んでいきます。
最初の共同経営者エドワード・ラッカーと1年で別れた後、初期の組織で主だった人物は、先述のケイト・ウォーン、ジョージ・H・バングス、チモジー・ウェブスターの3人でした。
探偵の採用に当たっては、誠実さ・潔癖さと裁判のための論理的常識を重視したようです。
職務内容の不明瞭な新聞広告で募集をかけ、さまざまな経歴の人を採用しました。
世間のイメージと違って報酬は高くはなく、多くの従業員を短期間に解雇・退職で入れ替えていました。
1867年には「ピンカートン探偵社の一般原理」という行動規範を作成し、探偵の教育を徹底します。
対立関係にある政党からの同時受任はしないとか、不正な謝礼は受け取らないという項目があるのは納得できますが、離婚・不倫などの女性問題は扱わないという項目があるのは興味深いです。
現代日本の探偵の主要業務は浮気調査だからです。
ピンカートンは、行動規範を徹底浸透させ、探偵の逸脱を警戒し、報告の正確性を追求しました。
深酒を禁止し、私生活においてまで規律と職業への奉仕を求めました。
1871年には火災に見舞われ、続いて脳卒中に倒れますが、ピンカートンは奇跡的に復活し、立派な社屋を再建します。
この頃、有名な標語「われわれは決して眠らない」が定められます。
その意味は、一人の探偵が眠っている間も別の探偵が起きて監視し、何があろうと「目」が追いかけていくということです。
「1873年恐慌」という金融危機のさなかにも強気の業務拡張を行います。
不況はだらだら続きましたが、労働争議が増えて、探偵社の仕事はかえって増えました。
労働スパイで栄えた彼らでしたが、逆に労働組合に摘発されることも増え、探偵が殺害される事件まで発生し、世の中は少しずつ移り変わっていきます。
第4章 私立探偵のイメージ
南北戦争後、探偵のスパイ活動、秘密主義、おとり捜査などが暴露されると社会から糾弾を受けました。
19世紀のアメリカ社会は警察権の拡大と市民権の制限を嫌い、戦時中は容認したことにも拒絶反応を示すようになりました。
そのため州境を越えて捜査権を持つ連邦警察は1908年までできませんでした。
全国的な捜査ができる私立探偵は、需要が大きいとともに、卑怯な集団というグレーイメージも伴ったのです。
一方で、賄賂を要求しがちな公警察に対して、ストイックに任務を遂行するポジティブなイメージを持つ人もいました。
戦後、私立探偵社が増えて競争が激化します。
業界を代表するピンカートン探偵社は、質の低い競合と一線を画すイメージを守るように努力します。
過当競争で仕事にあぶれた探偵社は浮気調査に商機を見出すようになります。
離婚が容易になった社会でニーズは大きかったですが、証拠の捏造もしやすい調査なので、不正調査が増えて、探偵のイメージは悪化しました。
ピンカートン探偵社は列車強盗の逮捕で活躍していましたが、英雄視されることもある一方で、あまりに暴力的で強引なやり方は市民の反感を買っていました。
ニセ情報に基づいた襲撃を行った結果、大列車強盗のジェームズ一味ではなく、その家族を殺傷してしまい、長男ウィリアムは殺人罪で起訴されます。
敗戦者であり、裕福な鉄道資本家に反感を持つ南部人にとってジェシー兄弟は義賊になりました。
ピンカートンは企業イメージの向上を目的に、探偵小説を次々に発表します。
彼がアウトラインを示してゴーストライターたちに書かせたのです。
主人公は、エドガー・アラン・ポーのデュパンのように部屋にこもって名推理で解決したりせず、聞き込みを繰り返して事実の積み重ねで事件を解明しました。
しばしば目的のために手段を択ばない暴力的な行動を取り、ピンカートンは正義のためなら微罪は許されるはずと考えていましたが、世間の反応は必ずしもそうではありませんでした。
彼の小説はフランスのビドクの「回想録」の影響も受けています。
ビドクは革命期に政府のスパイをやった後、パリ警視庁で有名な刑事部長になった人物で、引退後にこの本を書きました。
初期のピンカートン社の犯罪摘発は不正や着服が主なものでしたが、この頃、列車強盗・至急便強盗・銀行強盗などの常習犯の逮捕にも大きな成果を上げるようになります。
当時の公警察は他の州での犯罪情報を持っていませんでした。
それに対し、ピンカートン社は全国的な犯罪情報データベースを作ったので、圧倒的な検挙実績を上げることができたのです。
1870年代までに指名手配された泥棒の写真と資料を大量に保有して整理していました。
第5章 資本家の騎士団
アラン・ピンカートンと妻ジョーンの間には7人の子供が生まれましたが、生き残ったのは3人だけでした。
自身は愛人を作っているくせに、家庭では厳格な父親でした。
長男ウィリアムは飲酒癖が問題で父親の監視下に置かれますが、徐々に裏社会の顔ききとなり、「目」という異名をつけられます。
次男ロバートは大学でビジネスを専攻したインテリで、巡回警備事業を強化するよう主張して、父・兄と対立します。
1884年にアランが死ぬと、経営は息子たちのカラーに変わり、秘密主義から公開主義になり、ピンカートン探偵社は新たな方向性で発展していくことになります。
ジェームズ一味の摘発に失敗して世間の批判も浴びたこと、さらに鉄道警察が整備されつつあったこともあって、ピンカートン社は列車強盗逮捕事業から手を引いていきます。
アランの生前も死後も継続して主力業務のひとつだった労働組合つぶしで有名なものとして、1875年のモリー・マガイアズ事件があります。
これは鉄道会社の労働運動をアイルランド系テロ秘密結社モリー・マガイアズの陰謀だと決めつけて潰そうとする経営者のたくらみに、ピンカートン探偵社が加担したものです。
この事件はコナン・ドイルの小説「恐怖の谷」の元になり、ショーン・コネリー主演の「男の闘い」で映画化もされました。
アラン・ピンカートンはこの事件を「モリー・マガイアズと探偵団」という本にし、半ノンフィクションというジャンルを自作して、都合のいいことを書きます。
資本陣営は労働運動の高まりをよそ者による陰謀と決めつけ、ピンカートンはそれに協力したのでした。
この頃、「共産主義」が英語になり、ピンカートン自身も労働運動は共産主義者の陰謀だと思い込んでいましたが、実際は労働者はイデオロギーによって動かされていたのではなく、困窮した果ての抵抗でした。
ほかにもごろつきを集めた警備隊を送り込んで暴力沙汰を起こし、スト破りを請け負って稼いでいました。
しかし、1892年ホームステッドのカーネギー製鉄所の件では警備隊が労働者に襲撃されて敗北し、引き回しの上、激しい暴行を受けました。
この失敗で同社は15万ドルの損害と深刻なイメージダウンを被ります。
私警察を規制する法律も次々にできて、労働運動制圧のマーケットは縮小していきます。
第6章 犯罪資料のデータベース化
合衆国憲法で保証された労働者の権利を侵害する労働スパイ業務は、世間の評判が悪いだけでなく、先がない。
そう判断したピンカートン社は常習犯の逮捕業務に舵を切ります。
ヤミ賭博の摘発。競馬協会と契約して競馬場の群衆の中で活動するスリの摘発を行う業務。
宝石商連盟の公認警備会社として、宝石のセールスマンを強奪から守ること。
銀行連盟とも契約して銀行強盗、コソ泥、夜盗の防止を請け負い、成功を収めます。
公警察との関係は、ニューヨークのように競合する場合もありましたが、むしろ連携する場面が増えました。
ピンカートン社は、犯罪者の写真や身体的特徴などのデータベースを作っていました。
これに倣い、公警察でも全国犯罪情報センターを創設しようという動きがでてきます。
どんな情報を重視して収集するかですが、「ペルティヨン鑑識法」という人体測定学に基づく方法論が基本案でした。
しかし、これには色々な意見があって、話はなかなか前進しませんでした。
そんな折、ロンドン警視庁が1901年に指紋採取法を採用します。
同庁の支局長と交流のあったウィリアム・ピンカートンはすぐ指紋採取法に精通しました。
1903年に同姓同名で同様の体格の2人の囚人がみつかったことでペルティヨン鑑識法は絶望的になり、ウィリアムは指紋採取法を採用するよう公警察に働きかけます。
1911年のある裁判以降、米国では指紋が犯人特定の主要な証拠になっていきます。
公警察の全国犯罪データベースはまもなくFBIという形で結晶化します。
ピンカートン探偵社はそれに大いに貢献したのですが、名誉ある形でFBIの形成プロセスに組み込まれていたため、FBIが完成してしまえば自分たちの仕事がなくなることにはまだ気づいていませんでした。
第7章 泥棒逮捕に前科者を使う
1880年代は弟ロバートのニューヨーク事務所の全盛期で、産業家・宝石商・銀行家と強力なコネクションを形成してスパイ業で栄えました。
1890年代以降は裏社会に顔が利く兄ウィリアムのシカゴ事務所が力を振るいます。
銀行強盗などの常習犯の逮捕に成果を上げ、同時に彼らの社会復帰にも手を貸します。
このおかげで公警察と前科者の双方に太いパイプができました。
1900年代に入ると「渡りの泥棒」という新タイプの犯罪者が急増しました。
彼らは広く移動し、町に住まずに労働者のキャンプで暮らし、ニトログリセリンで金庫を爆破する手口を使います。
身元不明で情報収集が困難であり、ピンカートン探偵社には脅威でした。
1890年代末から1900年代にかけて、ピンカートン探偵社は通信に暗号を導入しています。
例えば依頼人や仲間は「メイ・ウッド」など「ウッド」で終わる名前、泥棒は「ダック・ストン」など「ストン」で終わる名前で呼びました。
20世紀に入り、ピンカートン探偵社は成長のスピードを増しました。
1883年までは3つだったオフィスが1909年には35か所に。その1/3は中西部にありました。
この時期、競合も急増します。
特に新参のバーンズ社は強力なライバルになりました。
しかし、数から言えば暴利を貪る悪徳探偵社の方が圧倒的に多く、業界の評判は非常に悪いものでした。
第8章 工作員アラカルト
この章の前半ではピンカートン探偵社の会社組織や従業員の報酬など、珍しい情報が提供されています。
後半は、超人的でかっこいい創作世界の探偵とは真逆な、ドジで平凡で、しばしばいいかげんだったりする探偵の実態の実例です。
探偵による暴露本もいくつか出て、ピンカートン探偵社は争います。
世の中は民主主義・公開主義の方向に進み、秘密主義で目的のために手段を選ばない探偵の時代は終わりを迎えようとしていました。
第9章 雨後の竹の子
1907年に弟ロバートが死去すると、兄ウィリアムが遅咲きの才能を開花させ、探偵業界のスポークスマンとしても活躍します。
その後、経営はアラン・ピンカートン・Jrが継承します。
ピンカートン探偵社は20世紀初頭には世界最大の探偵社になっていました。
従業員の独立開業もありましたが、積極的に支援しました。
ピンカートンの系列以外の探偵社も増え、20世紀の最初の20年間は参入ラッシュとなりました。
この中でバーンズ探偵社だけが強力なライバルに成長し、ピンカートン探偵社としのぎを削ります。
1908年、司法省の中に後のFBIの母体になる「捜査局」が創設され、その後の10年間で業務を拡張していきます。
1924年に捜査局長に就任したエドガー・フーバーは、改組されたFBIの初代長官となり、48年間に渡って君臨します。
その間にFBIは大統領をも動かす強力な機関に成長し、フーバーはそれを私物化します。
私立探偵は圧迫され、探偵業の地位向上とインチキ探偵の排除を目的とした国際シークレット・サービス連盟が1921年結成されます。
しかし、ピンカートン探偵社はもはやその中心にはいませんでした。
エピローグ
1926年に就任した4代目社長はピンカートン一族最後の人となります。
ほどなく捜査業務から撤退し、警備保障専門の会社になります。
1964年にはニューヨーク万博の警備という史上最大の民間警備契約を受注します。
社名も「探偵」を抜いてピンカートン社に変更。
19世紀末に後のFBIのようなポジションで発展した世界最大の探偵社は、ガードマンに転身したのでした。
現在は、年商10億ドル、世界20か国に220の支店を持つ多国籍巨大警備保障企業になっています。
日本の探偵業界の歴史
世界的に有名だったピンカートン探偵社の歴史は興味深いものです。(現在は世界的な警備会社になっています。)
その歴史は連邦警察的な仕事から始まったといえます。
19世紀までのアメリカの警察は管轄が州単位だったが、産業と鉄道の発達とともに州をまたがる人の移動が増えた。
連邦警察的なものが必要になったが、干渉と増税を嫌う独特な風土からなかなかそういうものが公警察として作れなかった。
そのニーズを埋めるものとして探偵社が発達したのです。
日本をはじめ、他の多くの国では最初から全国的・中央集権的な警察が発達しているので、その環境で生まれた探偵業は米国のものとは大きく異なります。
では、日本の探偵業界はどのような歴史をたどって発展してきたのでしょうか?
このトピックに関心がある方には、当サイトの下記の記事がおすすめです。
※本ページには広告リンク(PR)が含まれていますが、内容は取材や独自調査にもとづき、中立性を保持しています。
最終更新日:2026/1/17
更新責任者:徳野 制
管理記号:1
